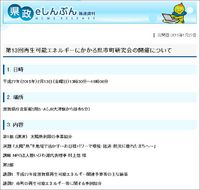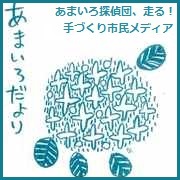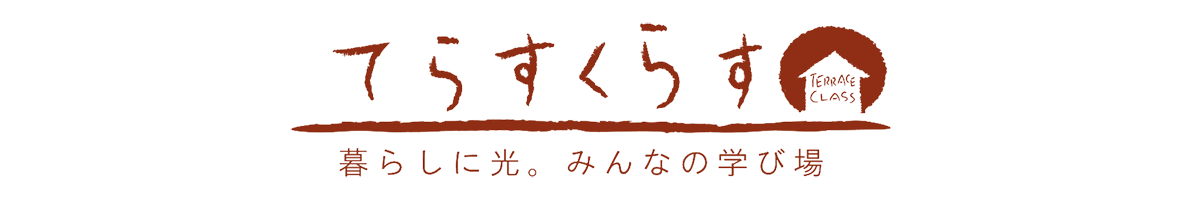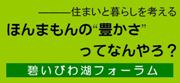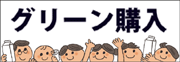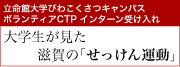雨水ネットワーク会議一日目
むらかみです。雨水ネットワーク会議2011in大阪の一日目がおわりました。
今日は大阪の「関西雨水市民の会」が実演されている子ども向けの環境学習プログラムの実演を見せていただいたり、各地の実践事例をお聞きしたり、ポスターセッションや交流会でいろんな方とお出会いしたりしました。

(メイン会場の様子)

(環境学習の実演)
今日感心したのは、大阪の設備会社の若い社長さんが、上記の市民団体の一員としてこどもたちの環境学習(演劇も交えて)をやっていらしているということでした。
また、大阪府の環境保全課で雨水利用に取り組んだきっかけが、若い職員さんからの提案だったという話も印象的でした。
「近畿水の塾」というNPOの学習会に参加して雨水利用に目覚められ、上記の市民団体と連携して雨水活用を広めることを提案されたそうで。
関西雨水の会も、「府がきちんと腰を据えて取り組むのなら」と条件を出して、その信頼関係の中ですすめられてきたそうです。
ポスター展示で目にした高槻市の雨水タンク地図はかなりの密度。これも、市の設置している環境市民会議の活動の賜物だそうです。

ひるがえって滋賀からは、残念ながら設備屋さんも、県や市町の職員さんもお見かけできませんでした。参加者340人(スタッフ60名含む)中、僕が把握する限りで滋賀からの参加者は4人どまりでした。
滋賀はびわ湖にたくさんの水があるけど、それを使うには大量のエネルギーを使います(東京都の場合、上下水道で全電力の2パーセントを消費しているとNHKラジオでききました)。
滋賀でも、もっと雨水活用を広めていきたい、と改めて思いました。
そしてそのためには、いろんな人たちの参加が必要だということも改めて感じました。
紙芝居や寸劇や漫画が得意な人、政策の得意な人、現場の設計・施工が得意な人…これからもいろんな方と一緒に、雨水の活用を広めていきたいと思います。(ので、一緒にやりますよ~、というお声かけ、お待ちにしております(^^))
ちなみに今日は、日本建築学会が発行したばかりの「雨水活用建築ガイドライン」も目にしました。雨水貯留浸透技術協会が近々発行される「雨水活用建築製品便覧」も。
市民団体、学者さん、メーカーさんなどが連携し、雨水活用が当たり前の時代に向かって動かれているのを実感しました。
あと一つ、おまけの話。
今朝、会場準備で大量の資料や記念品を運ぶ必要があり、その時にバケツリレー方式で運んだら、とっても楽にスムーズに運べました。
さらに、初めて会った人同士の仲もよくなって。
きっと震災地域では毎日のように繰り広げられてきた光景なのだろうな、と、被害に遭われている方のことに痛みを感じつつ、人と人とが息をあわせてつながることの力を、改めて感じました。
二日目の明日は分科会。「流域雨水ネットワーク」「雨水活用法制度」「雨水活用のアジア交流」の三つのテーマです。

(地下埋設型の大型雨水タンク)

(韓国からのゲストお二人。左-世界での雨水活用の映像を10年にわたって撮られている映像作家のファンさん、右-韓国での雨水活用の普及に取り組んでいるソウル大のハンさん)
今日は大阪の「関西雨水市民の会」が実演されている子ども向けの環境学習プログラムの実演を見せていただいたり、各地の実践事例をお聞きしたり、ポスターセッションや交流会でいろんな方とお出会いしたりしました。

(メイン会場の様子)

(環境学習の実演)
今日感心したのは、大阪の設備会社の若い社長さんが、上記の市民団体の一員としてこどもたちの環境学習(演劇も交えて)をやっていらしているということでした。
また、大阪府の環境保全課で雨水利用に取り組んだきっかけが、若い職員さんからの提案だったという話も印象的でした。
「近畿水の塾」というNPOの学習会に参加して雨水利用に目覚められ、上記の市民団体と連携して雨水活用を広めることを提案されたそうで。
関西雨水の会も、「府がきちんと腰を据えて取り組むのなら」と条件を出して、その信頼関係の中ですすめられてきたそうです。
ポスター展示で目にした高槻市の雨水タンク地図はかなりの密度。これも、市の設置している環境市民会議の活動の賜物だそうです。

ひるがえって滋賀からは、残念ながら設備屋さんも、県や市町の職員さんもお見かけできませんでした。参加者340人(スタッフ60名含む)中、僕が把握する限りで滋賀からの参加者は4人どまりでした。
滋賀はびわ湖にたくさんの水があるけど、それを使うには大量のエネルギーを使います(東京都の場合、上下水道で全電力の2パーセントを消費しているとNHKラジオでききました)。
滋賀でも、もっと雨水活用を広めていきたい、と改めて思いました。
そしてそのためには、いろんな人たちの参加が必要だということも改めて感じました。
紙芝居や寸劇や漫画が得意な人、政策の得意な人、現場の設計・施工が得意な人…これからもいろんな方と一緒に、雨水の活用を広めていきたいと思います。(ので、一緒にやりますよ~、というお声かけ、お待ちにしております(^^))
ちなみに今日は、日本建築学会が発行したばかりの「雨水活用建築ガイドライン」も目にしました。雨水貯留浸透技術協会が近々発行される「雨水活用建築製品便覧」も。
市民団体、学者さん、メーカーさんなどが連携し、雨水活用が当たり前の時代に向かって動かれているのを実感しました。
あと一つ、おまけの話。
今朝、会場準備で大量の資料や記念品を運ぶ必要があり、その時にバケツリレー方式で運んだら、とっても楽にスムーズに運べました。
さらに、初めて会った人同士の仲もよくなって。
きっと震災地域では毎日のように繰り広げられてきた光景なのだろうな、と、被害に遭われている方のことに痛みを感じつつ、人と人とが息をあわせてつながることの力を、改めて感じました。
二日目の明日は分科会。「流域雨水ネットワーク」「雨水活用法制度」「雨水活用のアジア交流」の三つのテーマです。

(地下埋設型の大型雨水タンク)

(韓国からのゲストお二人。左-世界での雨水活用の映像を10年にわたって撮られている映像作家のファンさん、右-韓国での雨水活用の普及に取り組んでいるソウル大のハンさん)
無農薬の、スイカの赤ちゃん。
Change Fuel, Change Feeling!
碧いびわ湖の総会2015&交流会報告
朝日新聞で綾さん宅のオープンハウスの記事が掲載されました。
「雨水の利用の推進に関する基本方針(案)」に関するパブリックコメントを提出しました
県と市町の職員さん向けに太陽"熱"活用のお話をさせていただきました。
Change Fuel, Change Feeling!
碧いびわ湖の総会2015&交流会報告
朝日新聞で綾さん宅のオープンハウスの記事が掲載されました。
「雨水の利用の推進に関する基本方針(案)」に関するパブリックコメントを提出しました
県と市町の職員さん向けに太陽"熱"活用のお話をさせていただきました。
2011年08月05日 Posted byaoibiwako at 22:20 │Comments(0) │▼疾る代表理事録(村上悟)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。