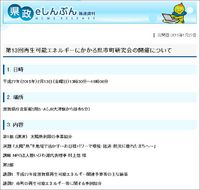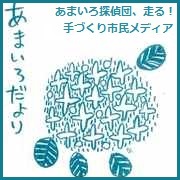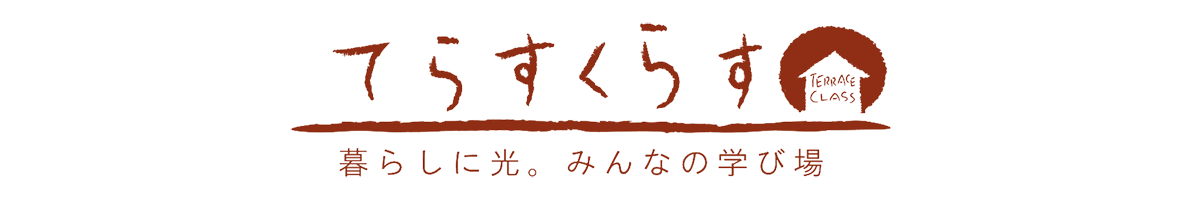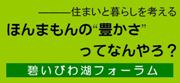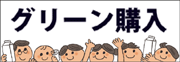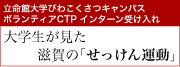大阪で「水道」をめぐるシンポに参加して
村上です。12月8日(土)、新大阪駅近くの会場で開かれた、「どうなんのん?大阪の水道シンポジウム 大阪−近畿−世界へとつながる水問題」にパネラーとして参加させていただきました。
(開催案内)http://www.water-policy.com/2012/11/128.html
そのときの記録を、共催団体NPO法人AMネットの澤口敬太さんが要約してくださっていますので、詳細はこちらをご覧ください。
(ブログ:偽百姓の日々)http://d.hatena.ne.jp/nice100show/20121208/p1
***今回のシンポの概要と感想***
主催はNPO法人水政策研究所という、大阪市水道労働組合の活動の中から生まれたNPOで、主催者も参加者も多くが市の水道マンさんという集まりでした。
栗東で自然農をされている嶋崎さんという方が、どっぽ村の清水さんとつながられたご縁で、今回のお話をいただき、メイン講師の水ジャーナリストでスロービジネススクールの講師でもある橋本淳司さんをはじめ、水政策研究所のみなさん、パネラーの山本奈美さん、コーディネーターの佐久間智子さんなど、いろいろな方と、出会い、議論し、親交を深めることができました。
市と府の水道事業の統合をめぐる政治的な動きに関する議論もさることながら、そこに終始せず、流域全体での水文化、水道事業そのもののあり方など、より根本的な課題についても視野を広く持って議論し、自分たちの進むべき道を見定めていこうとされている水政策研究所のみなさんの志に触れて、心が熱くなりました。(パネラーをされていた元水道マンの四条畷市議さんも、組合の執行副委員長さんもすでに雨水利用を自宅で実践されていて、懇親会でもそのことをすごく誇らしげに楽しげに話してくださいました!)
また、国際的な活動をされているNGOの方々や、私たちのようにローカルな活動をしているNPO、そして水道事業という現場で働かれているみなさん、それぞれ、違うフィールドで活動しているにもかかわらず、行き着く問題意識はつながっている、ということを確認し合える場でもありました。
また、昨今のエネルギーの問題と、水の抱える問題の、共通点の多いことも。
水、食料、エネルギーというインフラを、他人任せにせず、大きなものに依存しないで、自分たち自身でつくり、管理できる術と権利を手にすることの大切さを、改めて認識しました。
「琵琶湖・淀川でつながっているこの近畿から、新しい水の文化、暮らしの文化が生み出していけるのではないか?」という予感は以前から抱いてきましたが、その期待が、確信へとまた一歩、近づいた一日でした。
なお、メイン講師だった橋本淳司さんの講演が来る2月23日、大津であるそうです。主催は日本熊森協会滋賀支部さん。
具体的な事例やデータを引いて、明快にお話しくださいますので、約60分の講演も、あっという間です。これからの自分と水との関わり方を変えていきたい、と願うみなさんには、ぜひ一度、橋本さんのお話をお聞きになっていただきたい!と思います。
(橋本淳司さんのサイトはこちらです。http://www.aqua-sphere.net/index.html)
(開催案内)http://www.water-policy.com/2012/11/128.html
そのときの記録を、共催団体NPO法人AMネットの澤口敬太さんが要約してくださっていますので、詳細はこちらをご覧ください。
(ブログ:偽百姓の日々)http://d.hatena.ne.jp/nice100show/20121208/p1
***今回のシンポの概要と感想***
主催はNPO法人水政策研究所という、大阪市水道労働組合の活動の中から生まれたNPOで、主催者も参加者も多くが市の水道マンさんという集まりでした。
栗東で自然農をされている嶋崎さんという方が、どっぽ村の清水さんとつながられたご縁で、今回のお話をいただき、メイン講師の水ジャーナリストでスロービジネススクールの講師でもある橋本淳司さんをはじめ、水政策研究所のみなさん、パネラーの山本奈美さん、コーディネーターの佐久間智子さんなど、いろいろな方と、出会い、議論し、親交を深めることができました。
市と府の水道事業の統合をめぐる政治的な動きに関する議論もさることながら、そこに終始せず、流域全体での水文化、水道事業そのもののあり方など、より根本的な課題についても視野を広く持って議論し、自分たちの進むべき道を見定めていこうとされている水政策研究所のみなさんの志に触れて、心が熱くなりました。(パネラーをされていた元水道マンの四条畷市議さんも、組合の執行副委員長さんもすでに雨水利用を自宅で実践されていて、懇親会でもそのことをすごく誇らしげに楽しげに話してくださいました!)
また、国際的な活動をされているNGOの方々や、私たちのようにローカルな活動をしているNPO、そして水道事業という現場で働かれているみなさん、それぞれ、違うフィールドで活動しているにもかかわらず、行き着く問題意識はつながっている、ということを確認し合える場でもありました。
また、昨今のエネルギーの問題と、水の抱える問題の、共通点の多いことも。
水、食料、エネルギーというインフラを、他人任せにせず、大きなものに依存しないで、自分たち自身でつくり、管理できる術と権利を手にすることの大切さを、改めて認識しました。
「琵琶湖・淀川でつながっているこの近畿から、新しい水の文化、暮らしの文化が生み出していけるのではないか?」という予感は以前から抱いてきましたが、その期待が、確信へとまた一歩、近づいた一日でした。
なお、メイン講師だった橋本淳司さんの講演が来る2月23日、大津であるそうです。主催は日本熊森協会滋賀支部さん。
具体的な事例やデータを引いて、明快にお話しくださいますので、約60分の講演も、あっという間です。これからの自分と水との関わり方を変えていきたい、と願うみなさんには、ぜひ一度、橋本さんのお話をお聞きになっていただきたい!と思います。
(橋本淳司さんのサイトはこちらです。http://www.aqua-sphere.net/index.html)
無農薬の、スイカの赤ちゃん。
Change Fuel, Change Feeling!
碧いびわ湖の総会2015&交流会報告
朝日新聞で綾さん宅のオープンハウスの記事が掲載されました。
「雨水の利用の推進に関する基本方針(案)」に関するパブリックコメントを提出しました
県と市町の職員さん向けに太陽"熱"活用のお話をさせていただきました。
Change Fuel, Change Feeling!
碧いびわ湖の総会2015&交流会報告
朝日新聞で綾さん宅のオープンハウスの記事が掲載されました。
「雨水の利用の推進に関する基本方針(案)」に関するパブリックコメントを提出しました
県と市町の職員さん向けに太陽"熱"活用のお話をさせていただきました。
2012年12月10日 Posted byaoibiwako at 19:09 │Comments(0) │▼疾る代表理事録(村上悟)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。