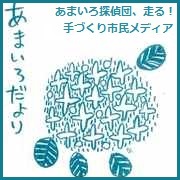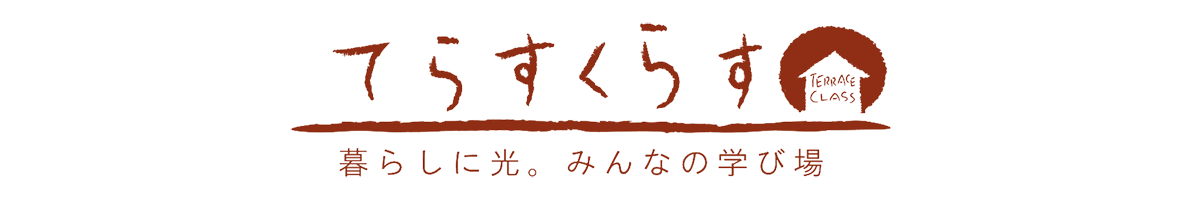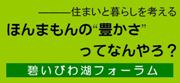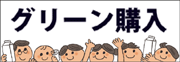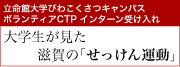ミカン山から省農薬だより
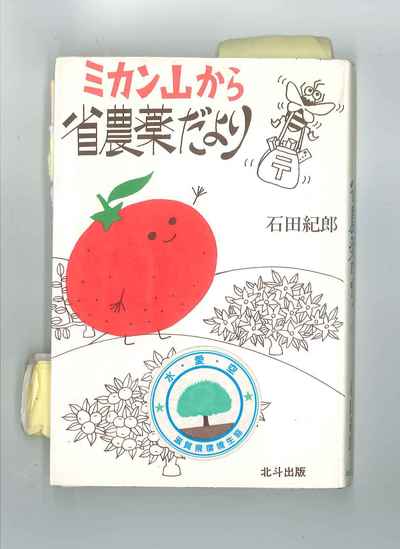
(書籍名)
『ミカン山から省農薬だより』
著者:石田紀郎
発行:北斗出版/1988年12月15日
著者略歴(本の発行当時):
1940年滋賀県の琵琶湖畔生まれ。1963年京都大学農学部
卒。1968年京都大学農学部大学院博士課程中退。現在、京
都大学農学部助手。植物病理学専攻。
1970年以来多くの公害問題にかかわる。琵琶湖汚染総合調
査団、琵琶湖淀川汚染総合調査団などに参加し、農薬汚染
の調査を継続している。「農薬裁判を支援する会」の事務局
を担当しながら、京大農薬ゼミの一員として省農薬ミカン園の
調査に参加。共著に「よみがえれ琵琶湖」「のみ水すて水かえ
り水」「枯れ死の里より」など。
※本の紹介
ミカン園の農薬散布で、一人の少年が中毒死して20余年。そ
の裁判に関係した著者は、農薬の現実にひき寄せられ、省農
薬への途を農学の目と足でさぐった。本書は、その調査をもと
に、筆執された。
* * *
(以下は、本の「まえがき」を紹介します。)
まえがき
わが国の農薬使用量は60万トンにもなります。「農薬漬け」
農業と農産物のことが社会問題化してから長い年月がたちま
したが、本質的な解決のないままに、農地の単位面積あたり
の農薬使用量はふえつづけています。水道水の中まで農薬は
忍び込んできました。まして、農産物の輸入自由化で海外の
農産物を食べる機会が多くなればなるほど、見知らぬ国で見
知らぬ人がつくった物を食べることがますますふえていきます。
わが国の農薬を考えるだけでは問題は解決しなくなり、もはや
農業問題に出口がないのではないかとさえ思えるほどです。
そこで、農民を悪者に仕立てたり、自分だけ安全な物を求め
たり、あるいはみんな毒入りを食べているのだからと居直った
りします。しかし、そうしながらも、なんとかならないものかとみ
んなが悩んでいます。
私の友人に琵琶湖の漁師がいます。彼がとってくる琵琶湖
産の魚に含まれる農薬の分析を十数年つづけてきました。
琵琶湖周辺でつかわれる農薬の量は年間6,000トンにも
のぼります。分解するもの、大気中に飛散するもの、土のな
かに残留するものなどをのぞいてほとんどが琵琶湖に流れ
込みます。とうぜんのこととして、琵琶湖の水、土、魚に農薬
は残留します。とくに、魚の中に濃縮されて高い濃度で検出
されます。こんな調査結果を発表すると、魚の港価格は買い
たたかれて暴落します。それでいて魚の小売価格は安くはな
らないのですから、調査をすることは、将来的には漁民の利
益になると信じているのですが、短期的には漁民を泣かせる
ことだけになってしまうのです。とうぜん、私は漁師から恨ま
れる存在となりかねないので、魚の調査結果を公にすること
をちゅうちょするようになります。この友人の漁師は漁師仲間
と私との板ばさみになって悩むことになります。どうしたらよい
のかとよく話し合いますが、これといった解決策がないままに
います。
農薬をつかう農民の側にもおなじような問題があります。毒
物である農薬を多用する農業がつづくかぎりこの課題はつき
まといます。そうかといって農薬を使用しない農業をすぐに実
現することは不可能に近いことです。農民と消費者が共同し
て農薬を省く方向を模索する動きが各地で精力的におこなわ
れています。どれほど省けるのかはそれぞれの農業がおか
れている状況によってことなるでしょう。
私たちは、ミカン山で可能なかぎり農薬を省いて栽培すれ
ば、どのように病気や害虫が発生するかを10年間調査して
きました。生き物のミカン山が相手ですから、調査がいつ終
了できるのかわかりませんが、いままでにわかったことをま
とめて出版することにしました。
つかえば農民の体に悪い農薬、つかえば残る農薬ですか
ら、つかわないようにする以外に友人の漁師と悩まなくてす
むようにはできないでしょう。そのためのひとつの試みとし
て、農薬害からの脱出に少しでも役にたてばと思います。
この本は私もその一員である京都大学農薬ゼミがおこな
った調査を基礎にしてまとめたものです。
ぜひいちど、ミカン山におでかけください。カイガラムシや
テントウムシ、小さな蜂と健康なミカンが待っています。
(関連リンク)
京大農薬ゼミ
http://dicc.kais.kyoto-u.ac.jp/KGRAP/
* * *
■碧いびわ湖の共同購入■
仲田さんと京大農薬ゼミの省農薬みかん
→ご注文をおまちしています~♪
http://aoibiwako.shiga-saku.net/e682237.html