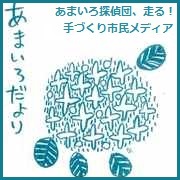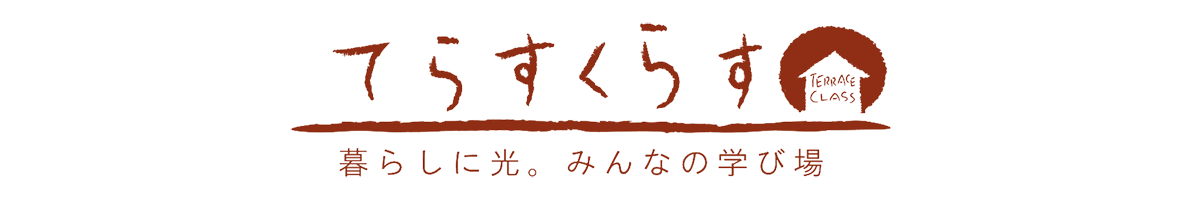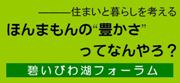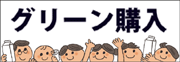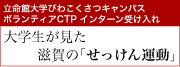小中学生たちの白熱議論!―3・11と働くことの意味
ねぎやまです。
フェイスブックで、面白い本が紹介されてました。
book.asahi.comの書評記事です。
読みたい本がまた1冊増えました・・(苦笑)。
* *

「僕のお父さんは東電の社員です」
―小中学生たちの白熱議論!
3・11と働くことの意味
[編]毎日小学生新聞
[著]森達也
[評者]中島岳志(北海道大学准教授)
[掲載]2011年12月18日
[ジャンル]人文
http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2011121800008.html
■根源を掘り起こす小学生の問いかけ
「突然ですが、僕のお父さんは東電の社員です。」
そんな書き出しの手紙が、毎日小学生新聞の編集部に届い
た。送り主は小学6年生のゆうだい君。彼は、元毎日新聞論
説委員の北村龍行が書いた「東電は人々のことを考えている
か」という文章に反論し、「読んでみて、無責任だ、と思いまし
た」と綴(つづ)った。
ゆうだい君は言う。原発を造ったのは、確かに東電である。
しかし、そのきっかけをつくったのは「みんな」ではないのか。
この「みんな」には、自分も、あなたも含まれる。だから、東電
だけのせいにするのは、無責任なのではないか。原発は「夜
遅くまでスーパーを開けたり、ゲームをしたり」している「みん
な」の欲望の産物なのではないか。
この問いに多くの小中学生が反応し、白熱した議論が繰り
広げられた。本書は、その記録に森達也の返答を付した一
冊である。
子供たちの反応は様々だ。ゆうだい君に同調する者もい
れば、「東電が悪い」「政府が悪い」と返す者もいる。しかし、
議論は次第に自己との対峙(たいじ)へと旋回していく。電
気に依存している自己の生活は何なのか? その生活を支
える私たちの欲望とは何か?
その問いの先に、子供たちは「私たちにできること」を探
しはじめる。節電、募金、話し合い、ヒマワリを植える、マス
クをする、ニュースを見る、勉強する……。答えは出ない。
しかし、子供たちは議論を通じて、一つ一つ認識を深め
ていく。東電バッシングのその先に、具体的な東電社員と
家族が存在すること。そして、原発が稼働する根底に、自
分たちの欲望が存在すること。一通の手紙が他者への想
像力を開き、自己と向き合うことを促す。人間は言葉の動
物だ。言葉が世界を動かし、人を動かす。
森達也は、ゆうだい君の言葉を受けて、子供たちに言う。
「本当にごめんなさい」と。
森は、自分が原発問題について何も発言してこなかった
過去と向き合い、一人の大人として謝る。そして、失敗を
繰り返さないために理由や原因を徹底的に考え、声を上
げる重要性を説く。しかし、社会は同調圧力に覆われ、な
かなか声を上げづらい。企業の中では、時に社益が優先
され、社員個人の意見や倫理が圧迫される。
では、私たちは一体、何のために働いているのか?
ゆうだい君の言葉は、次々に反響を繰り返し、根源的な
問いを掘り起こす。その連鎖は、読者を本源的な思考へ
といざなう。
自己の立っている場所を疑い、問いを発する。そんな大
切なことを思い起こさせてくれたゆうだい君に言いたい。
「ありがとう」
◇
現代書館・1470円/もり・たつや 56年生まれ。映画
監督、作家。映像作品に「A」「A2」、著書に『放送禁止歌』
『死刑』など。『A3』で講談社ノンフィクション賞受賞。
フェイスブックで、面白い本が紹介されてました。
book.asahi.comの書評記事です。
読みたい本がまた1冊増えました・・(苦笑)。
* *

「僕のお父さんは東電の社員です」
―小中学生たちの白熱議論!
3・11と働くことの意味
[編]毎日小学生新聞
[著]森達也
[評者]中島岳志(北海道大学准教授)
[掲載]2011年12月18日
[ジャンル]人文
http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2011121800008.html
■根源を掘り起こす小学生の問いかけ
「突然ですが、僕のお父さんは東電の社員です。」
そんな書き出しの手紙が、毎日小学生新聞の編集部に届い
た。送り主は小学6年生のゆうだい君。彼は、元毎日新聞論
説委員の北村龍行が書いた「東電は人々のことを考えている
か」という文章に反論し、「読んでみて、無責任だ、と思いまし
た」と綴(つづ)った。
ゆうだい君は言う。原発を造ったのは、確かに東電である。
しかし、そのきっかけをつくったのは「みんな」ではないのか。
この「みんな」には、自分も、あなたも含まれる。だから、東電
だけのせいにするのは、無責任なのではないか。原発は「夜
遅くまでスーパーを開けたり、ゲームをしたり」している「みん
な」の欲望の産物なのではないか。
この問いに多くの小中学生が反応し、白熱した議論が繰り
広げられた。本書は、その記録に森達也の返答を付した一
冊である。
子供たちの反応は様々だ。ゆうだい君に同調する者もい
れば、「東電が悪い」「政府が悪い」と返す者もいる。しかし、
議論は次第に自己との対峙(たいじ)へと旋回していく。電
気に依存している自己の生活は何なのか? その生活を支
える私たちの欲望とは何か?
その問いの先に、子供たちは「私たちにできること」を探
しはじめる。節電、募金、話し合い、ヒマワリを植える、マス
クをする、ニュースを見る、勉強する……。答えは出ない。
しかし、子供たちは議論を通じて、一つ一つ認識を深め
ていく。東電バッシングのその先に、具体的な東電社員と
家族が存在すること。そして、原発が稼働する根底に、自
分たちの欲望が存在すること。一通の手紙が他者への想
像力を開き、自己と向き合うことを促す。人間は言葉の動
物だ。言葉が世界を動かし、人を動かす。
森達也は、ゆうだい君の言葉を受けて、子供たちに言う。
「本当にごめんなさい」と。
森は、自分が原発問題について何も発言してこなかった
過去と向き合い、一人の大人として謝る。そして、失敗を
繰り返さないために理由や原因を徹底的に考え、声を上
げる重要性を説く。しかし、社会は同調圧力に覆われ、な
かなか声を上げづらい。企業の中では、時に社益が優先
され、社員個人の意見や倫理が圧迫される。
では、私たちは一体、何のために働いているのか?
ゆうだい君の言葉は、次々に反響を繰り返し、根源的な
問いを掘り起こす。その連鎖は、読者を本源的な思考へ
といざなう。
自己の立っている場所を疑い、問いを発する。そんな大
切なことを思い起こさせてくれたゆうだい君に言いたい。
「ありがとう」
◇
現代書館・1470円/もり・たつや 56年生まれ。映画
監督、作家。映像作品に「A」「A2」、著書に『放送禁止歌』
『死刑』など。『A3』で講談社ノンフィクション賞受賞。
春、野洲から守山の琵琶湖寄りあたり。雑観です。
「生きる」ということ 小出裕章さん 若い人へのメッセージ
近江八幡の水郷_北之庄の農場(百菜劇場)
守山で、ほたるが、ひっそり飛びはじめました。
栗東の竹林で「カスミサンショウウオ」!?
びわ湖・流域でたくましく生きる方に出会う
「生きる」ということ 小出裕章さん 若い人へのメッセージ
近江八幡の水郷_北之庄の農場(百菜劇場)
守山で、ほたるが、ひっそり飛びはじめました。
栗東の竹林で「カスミサンショウウオ」!?
びわ湖・流域でたくましく生きる方に出会う
2011年12月20日 Posted byaoibiwako at 07:00 │Comments(0) │▼配送員のひと言メモ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。